
通勤電車の中でも、仕事場の休み時間も、寝る前にもスマホを握りしめている方、多いと思います。アプリのゲームやSNSをしていれば退屈な時間はあっと言う間に過ぎていきます。
しかしそういうスマホ中心の生活には、どこか人間の深い部分を蔑ろにしているようなところがあります。
そこでこの記事では、忙しい情報社会の中で、生活全体を見つめ直すきっかけのために、あえて『日本文学』の傑作を読む事を提案したいと思います。
それでは、以下、オススメしたい小説です。
1きまぐれロボット:星新一
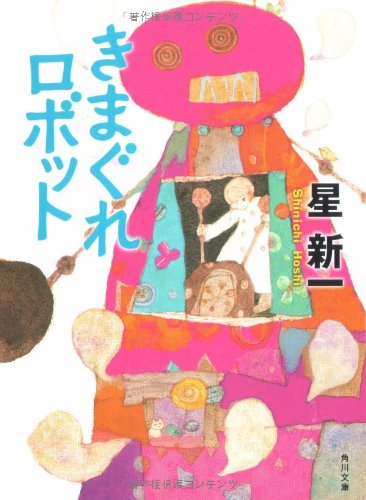
星新一は、短編より短いショートショートというジャンルの第一人者で、読みやすくてひねりのきいたSFの作品を数多く発表しています。読後感は「世にも奇妙な物語」にも似ています。
『きまぐれロボット』にはショートショート作品が31編収録されていますが、1作品はとても短いのであっと言う間に読み終えてしまいます。
あまり活字に触れたことが無い方にもおすすめできる一冊です。
2女生徒:太宰治
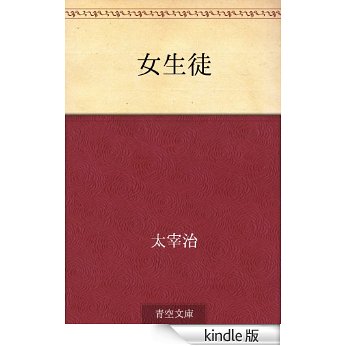
文学、というと彼の顔を思い浮かべる方も多いでしょう。太宰治。
太宰は作家活動の後期の、『人間失格』のような陰鬱な作風だけでなく、教科書にも載っている『走れメロス』のようなすぐれた短編も多く残しました。
『女生徒』は、14歳の少女が朝目覚めてから床につくまでの1日を、少女の独白体の文章でみずみずしく綴った作品です。思春期の微妙な心のゆらぎがとらえられていて、多くの女性が「どうしてこんなに女の人の気持ちがわかるの?」と思うそうな。
3伊豆の踊子:川端康成

日本の言葉の美を極めた作家、川端康成の代表作『伊豆の踊子』。
川端は新感覚派という文学の流派に分類され、写実的な文章を離れ、感覚にたよる文章によって物語を構成します。
『伊豆の踊子』は、伊豆を旅行する青年が、旅芸人の一座と道連れとなり、踊子の少女の純粋さに心惹かれていく様が描かれます。
物語に複雑な場面や構成はなく、日本語表現の美しさと技巧を。集中してじっくり味わえます。
4春琴抄(しゅんきんしょう):谷崎潤一郎

出典:Amazon
谷崎潤一郎の小説は高い芸術性とともに、女性崇拝やマゾヒズムの色濃い表現が見られ、やや手を出しづらいところがあるかもしれません「美」をめぐって豊富な語彙で紡がれる硬い文体は、それ自体が一つの美の極致をなしています。
『春琴抄』は、盲目の美少女・春琴と、彼女の身の回りの世話をする4つ年上の佐助の微妙な関係性の物語です。春琴は年上の佐助に対しても厳しく当たり散らし、佐助は彼女にひたすら平身低頭。谷崎の丁寧至極な場面描写や、息詰まるような物語の展開に、終始圧倒されます。
5偸盗(ちゅうとう):芥川龍之介
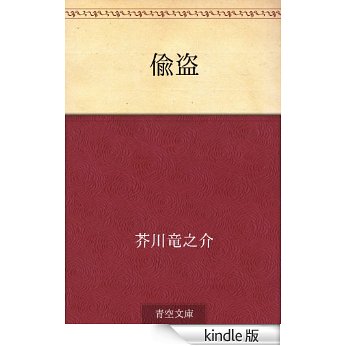
荒廃した平安の都を舞台に、盗賊団が貴族邸に討ち入るスペクタクルと、男女関係のこじれが並行して物語が進行する巧みな構成です。いきいきとした登場人物の個性や、疾走感のあるストーリーで、まるで映画を観ているような感覚に陥ります。
ちなみにこの『偸盗』は、高校の現代文の教科書などでおなじみの『羅生門』の続編とされていて、『羅生門』の最後に老婆の服を奪い去った下人が、本作では盗賊。人間のエゴイズムがどういう変化の過程を辿るのか? という視点でも読んでも面白いですね。
6桜の森の満開の下:坂口安吾
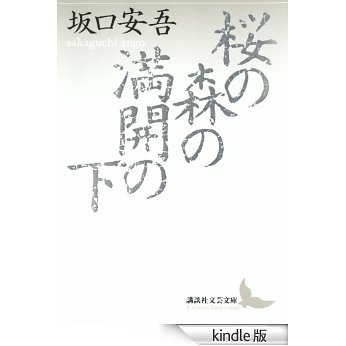
太宰と並んで無頼派と称された坂口安吾の作品には、いずれも美しさとともに、虚しさのようなものが同居しています。安吾は東京大空襲で崩壊する街並みと焼け野原を見て、いち早く戦後の本質を洞察しました。
『桜の森の満開の下』は、鈴鹿峠に暮らす山賊と、彼がさらってきた妖艶な女の奇妙な関係性の織りなす、暗い童話のような作品です。桜の花の美しさと、二人のむごたらしい生活の描写のコントラストが印象的です。それにしても、文学に登場するモチーフに美しい悪女が多いのはなぜなのでしょうか…。
7夢十夜(ゆめじゅうや):夏目漱石
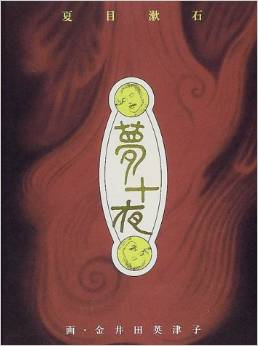
第一夜から第十夜まで、夢の光景が暗示的に綴られている、夏目漱石の『夢十夜』。
「他人の夢の話は脈絡がなくて聞いていてつまらない」ということもありがちですが、この短い小説の夢は美しい言葉と暗示的なメッセージによって、全く飽きることなく深読みができます。第一夜を読めば、あっという間に不思議な世界観の魅力の虜になること間違いなしです。
8すいかの匂い:江國香織

『すいかの匂い』は、11人の少女のそれぞれの夏を描いた短編集。「匂い」と記憶の間には、プルースト効果といって、強い結びつきがあることはよく知られていますね。この小説に登場する夏の描写の端々に、わたしたち読者が忘れてしまった原体験が掘り起こされます。
傷つきやすい少女の感性が生々しく描かれており、触れてはいけない心の傷や秘密を、静かに打ち明けられるような作品です。
9高瀬舟:森鴎外
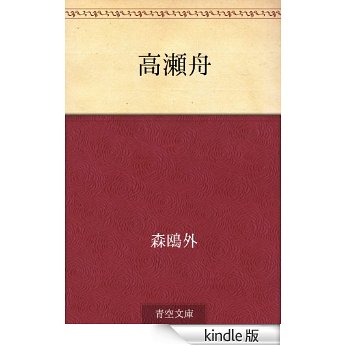
出典:Amazon
明治の文豪、森鴎外。鴎外は実は、東京大学医学部の一期生で、卒業後は軍医として働き、ドイツに留学もしています。こうした経験から、彼の文学の背景に西洋的な価値観と日本人の価値観の相克の問題が形作られていました。葛藤の中で編まれた小説の主題は現代でも普遍性を保ち、読んでみるとその思惑の深遠に驚嘆するばかりです。
『高瀬舟』で扱われる重要な問題に、「安楽死」があります。今日でも議論されるテーマを1916年(およそ100年前!)に描いていたというのです。明治時代を生きた文豪の思索に触れてみてはいかがでしょうか。
まとめ
ここまで、短編小説の名作をとりあげて紹介してきました。いずれも最新の作品ではありませんが、読み継がれてきた文学、傑作と呼ばれる作品には、どんな時代にも人間全体に通底するテーマがあります。そしてカンの良い方は、古い小説の中には、(当たり前ですが)携帯電話が出てこないのに気づくと思います。
ちなみに著作権が切れている作品は青空文庫で無料で読むこともできます。また青空文庫に掲載されていない比較的新しい作品も、500円前後で書店で買い求めることができます。
一人で過ごす時間、スマートフォンを置いて、日本文学の世界に浸ってみてはいかがでしょうか。